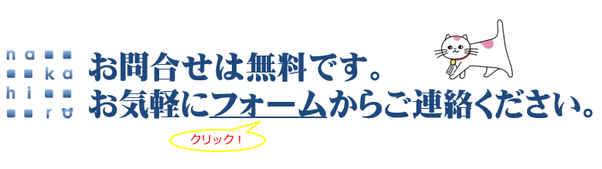共有物の変更・管理に関する見直し(一部)
各共有者は持分に応じて共有物を使用することが出来ますが、共有者相互の関係を調整するため民法には次のルールが定められています。
#共有物に変更を加える(農地→宅地など)には、共有者全員の同意を要する
#管理に関する事項(使用する共有者の決定など)は、各共有者の持分の価格の過半数で決する
#保存行為(補修など)は、各共有者が単独ですることができる
上記ルールの問題点として
1.共有物に軽微な変更を加える場合であっても、変更行為として共有者全員の同意が必要と扱わざるを得ず、円滑な利用・管理を阻害
2.賃借権等の使用収益権の設定は、基本的に持分の価格の過半数で決定できるが、長期間の賃借権等については全員の同意が必要と解されており、長期間かどうかの判断基準が明確でなく、実務上、慎重を期して全員の同意を求めざるを得ないため、円滑な利用を阻害
そのため、共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化が行われました。
共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持分の価格の過半数で決定することができる。こととなりました。
また、短期賃借権等の設定についての規律の整備も行われ、列挙されている期間を超えない短期の賃借権等の設定は、持分の価格の過半数で決定することができる。こととなりました。

多数の共有者が不動産を共有している場合、連絡をとっても明確な返答をしないままの共有者が出てきたり、所在等が不明になる共有者が出てきてしまったり、現在の共有者が誰であるのか分からなくなることが出てくるかと思います。
共有物に対して、修繕などの保存行為は単独でも行うことができますが、賃貸などの管理行為は共有持分権の過半数がなければできません。
また、売却やリフォームなどの変更(処分)行為は全共有者の合意がなければ行うことができません。
所在等不明共有者や賛否を明らかにしない共有者がいると、その不動産は売却・リフォームなどの管理・変更行為が一切できず宙ぶらりんの状態となってしまいます。
令和5年4月1日の改正により下記の通りとなります。

<所在等不明共有者がいる場合>
裁判所の決定を得て、
・所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができる
・所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる
<賛否を明らかにしない共有者がいる場合>
裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により管理に関する事項を決定することができる(変更行為は利用不可)
裁判所の決定を得る手続きについて
管轄裁判所はどちらの場合も、共有物の所在地の地方裁判所です。
賛否を明らかにしない共有者の場合についてのみ、事前の催告を行っていただき、書面等の証拠書類の提出が必要となってきます。
また、所在等不明共有者についても必要な調査を尽くしても不明であることを証明することが必要となってきます。
手続の流れ
<所在等不明共有者>
①所在調査
②申立て・証拠提出
③1か月以上の意義届出期間・公告の実施
④他の共有者の同意で変更・管理をすることができる旨の決定
⑤共有者間での意思決定
<賛否を明らかにしない共有者>
①事前の催告(共有者が他の共有者に対し、相当の期間(通常は2週間程度)を定め、決定しようとする管理事項を示したうえで、賛否を明らかにすべき旨催告)
②申立て・証拠提出
③1か月以上の賛否明示期間・通知(裁判所が対象共有者に対して賛否明示期間内に明らかにすべき旨を通知)
④他の共有者の同意で管理をすることができる旨の決定
⑤共有者間での決定
上記のルールは相続によって遺産に属する財産が相続人に共有されている場合(遺産共有)にも適用されます。
行政書士が裁判所提出書類(添付書類を含む。)を作成したり、作成の相談に応じることは出来かねますが、相続人の調査などの相続に関する業務につきましてはお引き受け可能となりますので、ご不明なことがあれば、一度当法人へご相談ください。